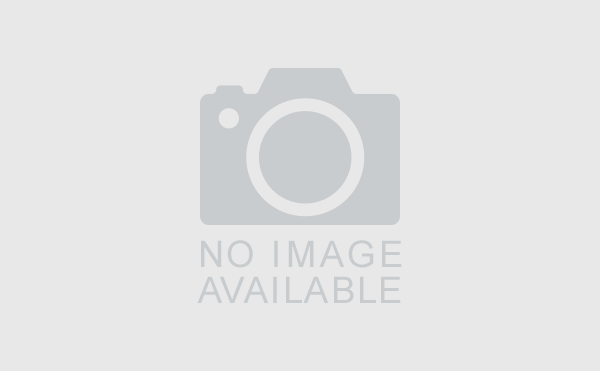2/16(日)
今日のご利用【来室1名】
水鏡天満宮でお祀りしている菅原道真公と梅のいわれを書いておきます。
(写真は太宰府天満宮の「飛梅」です)
平安代の貴族・菅原道真は、平安京朝廷内での藤原時平との政争に敗れて遠く大宰府へ左遷されることとなった延喜元年(901年)、屋敷内の庭木のうち、日頃からとりわけ愛でてきた梅の木・桜の木・松の木との別れを惜しんだ。
その時、梅の木に語りかけるように詠んだのが、次の歌である。
「東風(こち)吹かば にほひをこせよ 梅花(うめのはな) 主なしとて 春を忘るな」『拾遺和歌集』巻第十六 雑春。
現代語訳:東風が吹いたら(春が来たら)芳しい花を咲かせておくれ、梅の木よ。
「大宰府に行ってしまった主人がもう都にはいないからといって、春の到来を忘れてはならないよ」
伝説の語るところによれば、道真を慕う庭木たちのうち、桜は、主人が遠い所へ去ってしまうことを知ってからというもの、悲しみのあまり、みるみるうちに葉を落とし、ついには枯れてしまったという。
しかして梅と松は、道真の後を追いたい気持ちをいよいよ強くして、空を飛んだ。
ところが松は途中で力尽きて、兵庫県神戸市の後世「飛松岡」と呼びならわされる丘に降り立ち、この地に根を下ろした。(飛松伝説)
一方、ひとり残った梅だけは、見事その日一夜のうちに主人の暮らす大宰府まで飛んでゆき、その地に降り立ったという。(飛梅伝説)
出典: 「飛梅」, Wikipedia, CC BY-SA 3.0(URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/飛梅)
明日から寒くなるようです。
春が待ち遠しいですね。
おやすみなさい。
(山口)